蛍光灯の明かりがまぶしいことも苛々を増幅させる。今日が普通の日だったら、こんな小さなことにいちいち腹を立てることもなかっただろう。電車が停まり、両隣のアルコール臭い人たちが降車した瞬間、一気に緊張がゆるむ。シートに沈むように行儀の悪い姿勢でだらりと座りながら、誰もいない目の前の窓を眺める。街灯や自販機の光と、窓に映る自分の姿が重なる。焦点をどこにも合わせず、視界をぼんやりとさせると、だんだん眠くなってくる。かと思いきや、今日のゴミみたいな出来事が再び、まざまざと蘇ってきた。
__________
バイトが終わり、帰る支度をしながらスマホを確認するとマユコからラインが来ていた。
『助けて!』
こちらの既読がついたのを確認したのか、すぐに着信があり、
「もしもし、先輩!?今すぐ助けて!お願い!住所送るからすぐ来て!大変なの!」
マユコはマシンガンのごとく一方的に喋り、一方的に電話を切った。それからすぐにどこの何かも分からない住所と『おねがい』と書かれたふざけたスタンプが送られてきた。返信しても既読はつかない。あいつに関わるといつもろくなことがないことから、今回もどうせしょーもない何かだろうと推測する。きっとデメリットしかない。
だるい気持ちが8割、無視して何かあったらどうするよという気持ちが2割、そして8割は2割に負けた。
送られてきた住所に向かうと、そこは繁華街の居酒屋だった。嫌な予感しかしないけれど、もし本当に危機なのだとしたらそれが飲み屋で起きている可能性は全然ある。店の前から電話をかけてみる。
「もしもし?今店の前にいるけど、場所ってここで合ってる?ていうか大丈夫?」
「あっ!来た〜?ちょっと待ってて!」
「は?無事なの?」
店の入り口からスマホを耳に当てたマユコが出てきた。
「先輩待ったよ〜、ほら早く早く!」
わけも分からないままマユコに背中を押され入った店内は、酔った客たちの大きな声が充満している。
「その格好なに」
「は?いつも通りだけど」
「変なの」
お気に入りのトラックジャケットを侮辱されながら通路を奥へと進む。
「お待たせしましたぁ」
マユコが知らない集団に声を掛けると、一斉に視線がこちらに集まる。複数人の男女たちが知らない生き物を見るかのようなキョトンとした顔で自分を見ている。一瞬、時が止まったかのように感じた。
「…マユコちゃんの友達?初めまして」
誰?と思いながらも会釈をする。
「何?あんた無事なの?助けてって何?」
マユコに向かって早口で疑問をぶつける。
「何って見ればわかるでしょ、合コン」
席に着いた見知らぬ男女たちはまだずっとこちらを見ている。
「は…?」
「ほら先輩早く座って」
「…?」
瞬時に頭に血が上り、指先が冷たくなるのを感じた。安易に助けてという言葉を使ったこの女への怒りと、そいつを信じた自分に対する情けなさと、見世物にされているようなこの状況と、とにかくいろんな感情がらせんを描くようにぐるぐる駆け上り、声になって体外に出た。
「死ね!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」
またしても時が止まった。賑やかな店内が一瞬静まり、箸が食器に当たるカチャ…という音だけがどこかで響いている。
「キャハハハハ、もう〜先輩ったら、ほらほらいいから座って、ビールでいいですか?」
何なだめとんねん。お前の蒔いた種やろが。何ちょっとお前が上からな感じ出してんねん。もう仕方ないんだからぁ、処理してあげるけど、じゃないねんて。ころすぞ。
「ここ座ります…?」
怯えた目で一人の女が声を掛けてきた。
「なんかすっごいなぁ、なんていうか、元気なキャラ?」
引き気味な感じを出しながら勝手にキャラ付けをしてくる男。ああもう帰りたいのだが。半ば強引に座らされ、合コンとやらが再開していく。勝手に注文された中ジョッキが目の前に置かれた。泡が消えていくのを数分無心で見つめる。帰りたい。なぜここにいるのか。
「それでえっと、マユちゃんの友達は、名前は?」
あのー参加してるつもりないんで質問しないでもらっていいですか?と心の中で返事する。このまま無視できたらどんなにいいか。
「海…」
「ウミちゃん?かわいい名前だね」
ちゃん…?かわいい名前…?初対面のただ名前を確認しただけの人にこんな感情抱くの失礼かもしれないけど、なんか、キモい…。
「ウミさんは、ボーイッシュ?な感じなんですか?」
ほんのり笑いを含みながら訊いてくる女。なぜ笑っている?
「え?何ですか?」
聞こえていたけど、わざと聞き返してみる。
「や、あの、服とかどこで買ってるのかなーって」
「服ですか?近所に捨てられてるのをよく拾ってますね」
なんかムカついたので嘘をつく。
「えっ…?」
「先輩嘘つかないで」
マユコがこちらを睨むのでキッと睨み返した。
目の前のビールは1㎖も減っていないものの、周りはずいぶんと酒が入り、声のボリュームが3割増になっている。心なしかボディタッチも目立ってきて、笑った勢いで相手の腕を叩いたり、手相見れるよとかほざいて手を握ったりしている。地獄かここは。
「ウミちゃんは?」
また視線がこちらに集まる。
「はい?」
「だから、理想の男のタイプは?」
はい出た。自分をヘテロセクシャルと自覚していない蛮人どものお決まりのやつ。他の人間も全員が異性を好きだと信じて疑わない無知無神経丸出しの質問。この状況で沸点低くならないわけがない。大人の行動としてはNGだろうけど、この場の空気を破壊したくてたまらなくなった。
「えーっと、恋愛はしないですね、恋愛至上主義の世の中、正直キモいと思ってます。しかも恋愛恋愛言ってるけど、結局ヤリモクですよね?この会だって。じゃあ面倒な前置きとかせずに誰と誰がヤるか最初から決めれば良くないですか?あ、皆さんのためにあみだくじ作りましょうか?」ほとんどの人は目を丸くしてこちらを見ている。一人だけ、ニヤけた男が酔った勢いで絡んでくる。
「ウミちゃん、恋愛経験ないってことぉ?処女なのぉ?」
カチン。
「あのー、勘違いされてるようなので説明しますけど、ていうかそもそもこういうこと見知らぬ人に言うのも嫌なんですけど、自分は女でも男でもないので。ノンバイナリーのアロマンティックなんで、あ、意味分かりますか?」
男はポカンとした顔で何も言わずこちらを見ている。
「ねぇ、てか先輩さぁ、全然女のコらしくしないし、マユが気ぃつかって呼んであげてんのにずっと態度悪いし!ひどくない!?」
ひどいのはどっちだよ、てか話聞いとけよ。なんで身体が女に生まれたってだけで、女でいることを強要されなきゃならないんだよ。
「死ね!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」
吐き捨てて急いで店を出た。疲れた。気持ちを静めるためにそのままひたすら4駅歩いて終電に乗った。スマホを見るとマユコからラインが来ていた。
『女のコは1人3000円だって。次会った時払ってね』
即ブロック。
__________
「あの、終点です…、あの…終点なので」
気がつくと眠ってしまっていた。目を覚ますと、泣き顔の金髪の青年が目の前にいた。
「あ…、良かった…。あの、寝てたみたいだったので…」
寝起きの脳でなんとか状況を把握しようとしている間に、青年は会釈して電車を降りて行った。後に続くように急いで降りて改札を出る。終電で寝過ごすなんて最悪だ。本当に最悪。始発まであと4時間近くある。駅では時間を潰せそうにない。仕方なく出口の階段を上ると、さっきの金髪の青年が柱にもたれて泣いている。ヤバい人かもしれない。でも、起こしてくれたのに、お礼を言っていないことに気付いてしまった。どうせ今日は最悪な日なんだから。ヤバい人だったら逃げよう。近づいてお礼を言うことにした。
「あの」
突然声を掛けたからか青年は肩をビクッとさせ、こちらを見る。
「さっきは起こしていただいて、ありがとうございました」
「あっ…いえいえ」
「あの、大丈夫ですか?」
「えっ?」
「泣いてるので…」
「あ、すみません、ヤバいですよね、怖いですよね、すみません、あ、大丈夫です」
そう言ってまたシクシクと泣いている。
「あの、泣いてるところ申し訳ないんですけど、この辺りで始発まで時間潰せるところってありますか…?」
「あ、えーと…あの、こんなこと言ったら怪しいって思われるかもしれないんですけど………ファミレス行きませんか?」
「はい?」
「一人だと、危ないと思うので…。あっ、何もしないので安心してください。説得力ないかもですけど…。僕も時間潰したくて…。」
赤い目でこちらを見つめる。
「もしかして乗り越しですか?」
「いや、僕は、最寄りここなんですけど、ちょっと、家に帰りたくなくて…。あ、嫌だったら全然、断ってもらって大丈夫なので」
この人も最悪な一日を過ごしたのだろうか。
「いいですよ、行きましょう」
なぜか知らない人とファミレスに行くことになった。
二人でデニーズに入る。深夜のファミレスはガラガラで活気がない。入り口のボタンを押すと奥から店員がやってきて、窓際のボックス席に案内された。向かい合って座る。青年はこちらにも見える角度でメニューのページをゆっくりとめくる。
「あ、ありがとうございます」
「いえ」
青年はデザートのページで手を止め、真剣にメニューを見つめている。
「甘いもの、お好きなんですか?」
「あっ、そうですね、でも、あんまり食べないようにしてて…でも食べちゃおうかな…うん、じゃあ、この一番すごいやつにします」
青年はメロンのパフェを指さす。
「ダイエットですか?痩せてるのに」
「仕事柄、食べ過ぎないようにしてて…」
「…ボクサーか何かですか?」
そう尋ねると、青年が笑った。
「確かにボクサー、減量しますもんね、でも僕絶対ボクサーに見えないですよね」
「えーっと…見えないかもしれない」
「ですよね。えっと、モデルをやっているので…」
青年はなぜか申し訳なさそうに肩をすぼめた。泣いていたのでよく分からなかったけど、確かに言われてみれば中性的な雰囲気で背格好も顔の造形も整っていて、いろんな服を着こなす姿が容易に想像できる。今もミリタリージャケットがよく似合っている。
「へえ!モデルですか、すごいですね」
「いえ全然そんなことは……あっ、注文します?」
「あっ、そうですね、じゃあチョコレートパフェにしようかな、あとポテトも。食べ過ぎか。でも食べちゃおう。へへ」
「へへ」
服装をからかわれる自分とは真逆の人。
「あの、言いたくなかったらいいんですけど、なんで泣いてたんですか」
自分にないものを持っている、恵まれているように見える人。
「好きな人に恋人ができて」
パフェが来るまで青年の話を聞いた。青年は『線』という名前で、自分より1歳年上ということ。10年以上ずっと片思いしている幼馴染がいること。その幼馴染と同居していること。彼は線の気持ちに気づいていないこと。彼に彼女ができたこと。それを数時間前に知ったこと。好きな人の幸せなのに素直に喜べないこと。帰って顔を合わせたら泣いてしまいそうだから帰りたくないこと。
「お待たせしました。マスクメロンのサンデーのお客様」
「はい」
線は小さく手を挙げる。チョコレートパフェとポテトもテーブルに置かれる。
「わぁ、すごい。メロンがいっぱい乗ってる。いただきます」
行儀よく手を合わせているのにつられて、自分も手を合わせる。
「いただきます」
線はパフェの上に乗った丸いメロンを一口食べると、少し腫れぼったい目を大きく開いた。
「おいしい!一口食べますか?あ、知らない人の一口は嫌ですよね、すみません」
「あ、じゃあ交換しましょう」
チョコレートパフェを差し出して、メロンパフェを一口食べる。
「ほんとだ、おいしい」
「ね!チョコもおいしい」
線は嬉しそうにしている。あんなに泣いていたのに。
数時間前の自分を思い出す。威勢良く、恋愛キモいと言い放った自分。何も知らずに決めつけて、自分と違うものを一緒くたにして、大げさに忌み嫌って排除するなんて。純粋に誰かを想ってる人もいるのに。恥ずかしい。これじゃあいつらと同じだ。
「よかったらポテト食べませんか」
「いいんですか?」
「どうぞ。ドリンクバーも頼もうかな」
「え、じゃあ僕も」
それから少しだけ自分の話をしたり、服の話をしたり、他愛のない話をしているうちに空がうっすら明るくなってきた。窓の外を眺めながら線が言う。
「そろそろ電車動いてるかな」
「そうかも。家、帰れそうですか?」
「うん。聞いてもらって、ちょっと元気になりました。ありがとう」
「ううん。よかった」
あくびが出た。それを見た線もあくびをした。
線は駅まで送ってくれた。友達みたいに手を振って別れた。

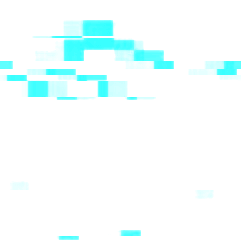
QWERTY


